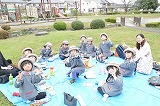2025年10月30日
りんご狩り
年少うめ組さんが、親子遠足でりんご狩りに行ってきました。
お部屋のカレンダーを見て当日を楽しみにしていた子どもたちは、気分上々でりんご園に向かいました。場所は宇都宮市石那田町の高橋りんご園さんです。
到着するとすぐに、りんごの試食会が始まりました。遠慮がちにりんごに手を伸ばす子どもたちでしたが、一口食べるとあら不思議!「美味しい!」「パパも食べてみて」「もう一個!」と勢い良く食べるようになりました。「お昼食べられるかな…」という保護者の心配をよそに、試食用のりんごをあっという間に完食してしまいました。りんご園で食べるりんごは、格別だったようです。



試食の後はいよいよ収穫です。
収穫場所に移動すると、たくさん実を付けた何百本ものりんごの木がを出迎えてくれました。
「えっ、すごい」「いっぱいある」と顔を見合わせながら、親子共々感動していました。
赤いりんごや大きいりんご、とても高い場所にあるりんごなどそれぞれが思う最高のりんごを求めて、思い思いに楽しみました。「こっちの方が絶対に良いよ」「もうこれ以上はいらないよ」と保護者と子どもたちのせめぎ合いもなかなかに見物でした。そんな親子の真剣な姿にほっこりしてしまいました。




りんご狩りの後は、ろまんちっく村に立ち寄り、昼食をとったりレクリエーションしたりしてのんびりと過ごしました。帰りのバスでは、たくさん動いて疲れてしまったのか寝てしまっている子もいました。


幼稚園に帰って一日を振り返ると、「楽しかった!」「また行きたい!」という声をたくさん聞くことができました。親子でバスに乗って出かけたり、たくさんりんごを食べたり、初めてのりんご狩りを体験したり、とても充実した一日を過ごすことができたようです。
10月は多くの園外保育を通して、秋の自然にたくさん触れることができました。もうすぐ冬を迎えますが、冬の遊びや楽しみ方も存分に満喫できるよう活動を考えていきたいと思います。
2025年10月27日
秋の遠足
気持ちのいい天候の中、秋の遠足へ行きました。
意気揚々と出発した子どもたちでしたが、どんどん道を進んでいくと「まだ?」「お腹空いた」など弱気な発言もちらほら聞こえました。目的地の「健康の森」が見えると、表情がパッと明るくなり、足取りも軽くなりました。



森に入ると、子どもたちは喜んでドングリやクヌギ、セミの抜け殻など秋ならではの自然物を見つけてはお互いに教え合ったり、見せ合ったりしていました。
その中でキノコに詳しいお友達がキノコを探し始めると、他のお友達もキノコ探しが始まり「ホコリダケ」というキノコを発見しました。触れるとホコリのようなものが舞う様子に、みんな興味津々でした。秋=木の実を連想しがちでしたが、キノコという新しいジャンルに目を向けると、たくさんの発見があり、より探索が楽しそうでした。




探索を楽しんだ後は、お待ちかねのお弁当タイムです。お弁当を食べたら子ども達の元気も復活!広い芝生で走ったり、踊ったり、寝転んだり…思い思いに過ごしていました。





楽しく遊んだ後は帰園です。帰り道にバスを見かけると「これに乗ったら幼稚園に帰れる?」なんて声も聞こえましたが、頑張ってみんなで歩いて帰りました。途中眠くなってしまい半目になってしまったり、目をつぶってしまったりする子もいましたが、幼稚園が見えると笑顔になり、全員で最後まで歩ききることが出来ました。
今まで興味がなかったものでも、お友達の影響を受け一緒に探す姿や、何もない広場でもお友達と一緒に遊びを生み出す様子を見て、集団生活においていかにお友達の存在が大切で偉大なものなのかを改めて感じました。最後まで歩ききれたのも、一緒に頑張った「お友達」がいたからなのではと思います。これからもお友達との関わりを更に深めながら、生活していって欲しいです。

園児の皆さん、引率してくださった役員さん、お疲れさまでした。
2025年10月22日
お芋掘り
近隣の方の畑をお借りして、今年もお芋掘りを行いました。
「大きいのとる!」「ご飯たくさん食べてきたからいっぱいとれるよ!」「早く畑行こうよ!」とやる気に満ち溢れた声がたくさん聞こえてきました。畑が見えると子どもたちの表情が一段と明るくなり、「たくさんできてる!」「土のにおいがしてきた!」と感じたことをたくさん話してくれました。
「全部とっちゃうよ!」と息巻いていた子どもたち、宣言通り全て収穫することができるのでしょうか?勢いそのままにお芋掘りスタートです。
掘り進めると湿った土がたくさん手にまとわりつき、飛び出してくる虫に阻まれ、大苦戦の子どもたち…。お芋一つ掘り出すのにもとても時間を要しました。時間がかかったからなのか、苦労したからなのか、掘り出せた喜びはひとしおで「大きいのとれた!」「見て見て!」「写真撮って!」と嬉しそうに報告してくれました。


「先生手伝って」「硬くて掘れない!」そんな声が聞こえた時には、ゆり組さんや周りのお友達が進んで協力して掘る姿もあり、見ていてとても頼もしく感じました。



約250本もの苗からできたたくさんのお芋は、子どもたちの手によって40分かけて全て収穫されました。時間はかかりましたが「全部とっちゃうよ」を達成することができました。本当によくがんばりましたね!
このお芋掘りを通して、肌で感じることができたと思います。この気持ちを忘れずどんな食べ物に対しても感謝の心を持ち、美味しくただいて欲しいと思います。
焼き芋、蒸かし芋、スイートポテト、楽しみ方も様々です。お芋をどんなふうに食べたのか、これから子どもたちのお話を聞くのがとても楽しみです。
2025年10月16日
JR日光線に乗る日
年長ゆり組のお友達がJR日光線で乗車体験をしてきました。
駅の仕組みや、電車の乗り方、公共施設でのマナーを体験することを目的としています。
宇都宮駅に到着し、まずは切符の購入です。硬貨をしっかり握りしめて、券売機で自分で購入します。出てきた切符を嬉しそうに見つめ「値段が書いてある!」「時間も書いてある!」「ちょっと固いね」「オレンジで後ろは真っ黒」「匂いするかな」と、小さな切符一枚でもたくさんの発見がありました。




購入した切符で自動改札を通ります。ここでも切符に変化がないか目を光らせる子どもたち。すかさず「穴開いた!」と穴をのぞいたり、穴をなでたりと変化を楽しんでいました。



改札を通過したら日光線の停まる5番線を探します。上にも下にも壁にも、たくさんの所に表示があり、すぐに見つけることができました。事前に図鑑で見ていた、新幹線やエレベーター、エスカレーターなどのマークもあちらこちらにあり、発見を楽しみながらホームへと降りていきました。


ホームへ降りてからも、子どもたちの興味は止まりません。色々な音や音楽が聞こえたり、放送が聞こえたり、みんなが乗る電車はどっちから来て、どっちに向かうのかを予想したり、向こう側の線路に停まっている電車を観察したり…子どもたちの五感は常にフル活動でした。
いよいよ乗車です。電車内でもたくさんの所に様々な表示があります。優先席に気付く子、吊り革に気付く子、乗車口の床に点字ブロックを見つける子、景色を楽しむ子、景色を見ながら踏切を数える子とそれぞれがたくさんのことを感じながらの乗車になりました。



降車後は、記念に切符を持ち帰れるよう、駅員さんにハンコを押してもらいました。

公園へ移動し、お昼を食べてたっぷり遊んで帰りました。公園からは「先生、富士山!」「東京タワーも見えるよ!」と近くの山や鉄塔がとても特別なものに見えたようで大興奮。たった二駅の乗車体験が、子どもたちにとっては、すごい大冒険だったのだなと感じました。
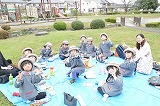





今回の園外保育は、発見を楽しみながらも、それに対してどうしてだろうと考える良い機会になりました。駅は色々な人が利用することから、みんなが使いやすいような仕組みになっていることにも自然と気付くことができました。これからも、色々なことに目を向けながら「なんでだろう」とたくさん考えてみましょうね。
2025年10月15日
防火の集い
10月9日㈭年中たんぽぽ組さんが、幼年消防防火のつどいに参加しました。
たんぽぽ組では消防車や火事についての絵本を読んで、当日に向けて気持ちを作ってきました。
防火のつどいが始まると、消防音楽隊による素晴らしい演奏に合わせ、歌や踊りを楽しみました。
その後は作新学院女子短期大学の学生による「アンパンマンのやきいもまつり」、宇都宮西消防署による「ヒケシレンジャー」を観劇しました。
火が出てくる場面になると「危ない」「怖い」という声も上がっていました。




最後は「ぼくたち わたしたちは ぜったい ひあそびはしません」と、会場の全員で誓いました。

外では消防車、消防士さんと写真撮影。
「乗ってみたいな~」「何かくるくる回っている」と車体に興味津々でした。


園に戻ってから、消火器や消火栓の場所を確認しました。
お遊戯室のカーテンが燃えない素材になっていることも知りました。

火事を起こさないためには、もし起きてしまった時には、ということを良く考えた一日でした。
防火の集いが防災について考えるきっかけとなるよう継続的に働きかけていきます。